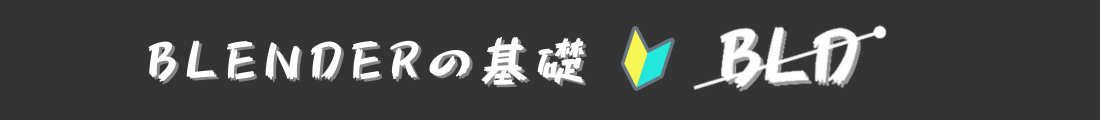入力
「入力」ノードは、オブジェクトの持つ内部データや外部環境の情報をシェーダーに取り込むための基礎です。
- アンビエントオクルージョン
簡易的な陰影効果を取得するノード。凹んだ部分や物体が密集している箇所を暗くでき、ディテール感や立体感を強調。高品質レンダリングではライトやGIで代替できるが、軽量表現やゲーム系マテリアルで便利。 - 属性
オブジェクトや頂点に付与された属性(頂点カラー、UVセットなど)を取得。外部ソフトで設定したカラーデータをBlender内で直接利用する際に必須。例:頂点ペイントした色をそのままマテリアルに反映。 - ベベル
ジオメトリのエッジに擬似的な丸み(ベベル)を生成。モデリングで細かく面取りせずに、レンダリング時だけ滑らかなハイライトを出せる。特に硬質プラスチックや金属表現で有効。 - カメラデータ
カメラとの関係情報(距離や角度)を取得。フォグ表現、視差エフェクト、奥行き依存の色変化などに利用可能。 - カラー属性
頂点カラーを扱う専用ノード。従来の「属性」ノードより直感的に使える。 - カーブ情報
パーティクルヘアやカーブオブジェクト用。毛の長さや根元~先端に応じた情報を取得し、毛先の色グラデーションや太さ変化を実現。 - フレネル
入射角に基づいて反射強度を返す。ガラス・水・金属など、見る角度によって縁が光る効果を作るときに有効 - ジオメトリ
法線、位置、バウンディング情報など、オブジェクト自体の座標系を取得。例:ワールド座標に応じたグラデーション、オブジェクトの上下方向で色分け。 - レイヤーウェイト
フレネルに似ているが、より汎用的な角度依存データを返す。輝きや輪郭ハイライトの調整に便利。 - ライトパス
レンダリングの光線情報を取得。「影だけ消す」「反射には映るけど直接は見えない」など、合成用途で重要。 - オブジェクト情報
オブジェクト固有のIDやランダム値を取得。同じマテリアルを複数オブジェクトに割り当てても、個別に色を変えるといった表現が可能。 - パーティクル情報
パーティクルシステムから寿命・サイズ・位置などの情報を取得。粒子ごとに色を変えるなど、動的エフェクトに活用。 - ポイント情報
ジオメトリノード用。ポイントクラウドやインスタンスの情報をシェーダーに渡すときに使用。 - RGB
単純に指定した色を出力するノード。基本的なカラーピッカーとして使用。 - タンジェント
法線とは異なり、表面の接線方向ベクトルを返す。異方性シェーダー(髪、ブラシ痕、金属ヘアラインなど)に必須。 - UVマップ
オブジェクトのUV展開情報を取得。テクスチャを正しく貼るための基盤。複数UVがある場合は切り替え可能。 - 値
単一の数値を出力。設定用のスライダー代わりに使用可能。色や強度を統一管理する際に便利。 - ボリューム情報
ボリュームシェーダーに関する情報を返す。光の減衰、ボリューム密度、炎や煙の制御に使用。 - ワイヤーフレーム
ジオメトリのワイヤーフレーム(エッジ)を出力。セルルックの輪郭線や、線画的な表現に有効。
出力
「出力」ノードは、マテリアルやレンダリングで最終的にどこに結果を送るかを決めるノード群です。
入力ノードが「情報を受け取る」ものだとすれば、出力ノードは「結果を渡す」役割を持ちます。
- AOV出力
AOV(Arbitrary Output Variables)=カスタムのレンダーパス出力。任意のマスクやエフェクト用の値をレンダリング時に書き出せる。コンポジットや外部ソフト(After Effects、Nukeなど)での合成調整に必須。 - ライト出力
ライト(光源)専用の出力ノード。通常の「マテリアル出力」とは別に、ライトの色や強さをカスタマイズできる。 - マテリアル出力
マテリアルの最終出口。すべてのシェーダーは最終的にここへ接続される。
「サーフェス」「ボリューム」「ディスプレイスメント」の3系統に分かれている。
カラー
「カラー」カテゴリは、入力された色(テクスチャやシェーダーの出力)を加工・変換するフィルター的な役割を持ちます。
- 輝度/コントラスト
入力カラーの明るさ(Brightness)とコントラストを一括調整できる。写真補正ソフトの基本機能と同じイメージ。 - ガンマ
入力カラーのガンマ補正を行う。値を大きくすると暗部が持ち上がり、明るい印象に。小さくすると暗く締まる。 - HSV(色相/彩度/明度)
入力色を Hue(色相) / Saturation(彩度) / Value(明度) で調整。フォトショの「色相・彩度」調整と同じ感覚。 - カラー反転
入力色を反転する(RGBを逆転)。白は黒に、青はオレンジに、といった具合に真逆の色を返す。 - 光の減衰
シェーダーで使う光の減衰を計算する特殊ノード。実際は「カラー加工」というよりライトの挙動調整に近い。 - カラーミックス
2つの入力カラーを合成する。合成モード(Mix, Add, Multiply, Overlay など)を選択可能。 - RGBカーブ
入力カラーをカーブ操作で調整。フォトショの「トーンカーブ」と同じ。各チャンネル(R/G/B)を個別に操作可能。
コンバーター
入力データ(色、数値、ベクトルなど)を「別の形式」や「使いやすい範囲」に変換して出力します。
テクスチャの制御、マスク処理、座標計算などで必須。
- 黒体
温度(ケルビン値)を入力すると対応する発光色を返す。低温 → 赤っぽい、 高温 → 青白い。
炎や電球の色を物理的に再現。 - 範囲制限
数値を指定した最小値~最大値に収める。例えば 0〜1 に制限すると「マスクのはみ出し」を防げる。 - カラーランプ
入力値(0~1)をグラデーションにマッピング。スライダーで色を自由に設定可能。 - カラー合成
R/G/B の数値を組み合わせてカラーを作る。 - XYZ合成
X/Y/Z の3つの数値からベクトルを生成。 - Floatカーブ
1つの数値をカーブ操作で調整。RGBカーブの「数値版」 - 範囲マッピング
入力値の範囲を別の範囲に変換。 - 数式
足し算、掛け算、三角関数など数値演算を行う。シェーダーで「ちょっとした数式処理」ができる便利なノード。 - ミックス
2つの値を混ぜる。「カラー」カテゴリの MixRGB と似ているが、こちらは数値やベクトルにも対応。 - RGBのBW化
カラーを白黒(輝度値)に変換。各ピクセルの明るさ情報のみを抽出できる。 - カラー分離
入力色を R/G/B に分解。HSLやHSVの分解も可能。 - XYZ分離
ベクトルを X/Y/Z の成分に分解。座標や法線ベクトルから特定方向の情報を取り出せる。 - ベクトル演算
ベクトルの加算・内積・正規化など。座標操作や方向制御に必須。 - 波長
波長(nm)を入力すると物理的なスペクトル色を返す。例:450nm → 青、600nm → 赤。
シェーダー
シェーダーノードは、オブジェクト表面や内部の見え方・光の振る舞いを決定します。
「表面シェーダー(BSDF系)」「透過系」「ボリューム系」に大きく分けられます。
- シェーダー加算
2つのシェーダーを加算して合成。光沢 + 透過、放射 + ディフューズなど。ただし「物理的に正しくない」場合もあり、過剰に使うと不自然になる。 - ディフューズBSDF
一般的な拡散反射(マットな質感)を再現。 - 放射
自発光するシェーダー。照明代わりにも使えるが、Eeveeではライトとしては働かず見た目が光るだけ - グラスBSDF
ガラスや透明な液体を表現。屈折と反射を両立する。サンプル数が多いとレンダリング重め。 - 光沢BSDF
鏡面反射を表現。金属やコーティングの「反射面」に最適。 - ヘアーBSDF
髪やファー専用シェーダー。繊維の複雑な光の反射を再現。 - ホールドアウト
透明な「穴」を作るシェーダー。アルファチャンネルにマスクとして書き出す際に使う。 - メタリックBSDF
金属質の反射を再現するシェーダー。ただし現状は「プリンシプルBSDF」で代用するのが主流。 - シェーダーミックス
2つのシェーダーをブレンド。0〜1の値やテクスチャで割合を制御。 - プリンシプルBSDF
オールインワンの標準シェーダー。ディフューズ、金属、透過、粗さ、全てまとめて扱える。
現代のBlenderでは基本的にこれ一択でOK。 - プリンシプルヘアーBSDF
髪専用のシェーダー。物理ベースで使いやすい。色やメランジ感(染色風)まで再現可能。 - プリンシプルボリューム
ボリューム表現(煙・炎・霧)用の統合シェーダー。吸収や散乱をまとめて扱える。 - レイポータルBSDF
光線を「別の場所へ転送する」特殊シェーダー。主に建築ビジュアライズで使う(窓の間接光を効率よく通す)。 - 屈折BSDF
ガラスの屈折部分だけを表現。反射は別途 Glossy を足す必要がある。 - シーンBSDF
布の「繊維が光を反射する縁の光沢」を再現。サテン、ベルベットなどに使う。 - SSS
半透明素材内部で光が散乱する効果。皮膚、牛乳、蝋、石鹸などに使える。 - トーンBSDF
セルルック(アニメ風)用シェーダー。影をクッキリとした境界で表現。 - 半透明BSDF
裏側からの光を透過させる。紙や葉っぱなどに有効。 - 透過BSDF
完全な透過を作る。アルファ合成のマスク用途で便利。 - ボリューム吸収
光がボリューム内部で吸収される効果。水にインクを垂らしたような色の濃さ。 - ボリューム散乱
光が内部で散乱して白く霞む効果。ミルクガラスや霧表現に利用。 - ボリューム係数
ボリューム表現に必要な係数データ。基本的には Principled Volume の方を使うことが推奨。
テクスチャ
テクスチャノードは「模様や画像」を生成・読み込みし、カラーや数値として出力します。
それをシェーダーに渡すことで、木目・レンガ・ノイズ・画像テクスチャなどの質感を表現できます。
- 複数の画像
複数の画像を切り替えて使用できるノード。UV展開されたオブジェクトに、アニメーションやバリエーションを与えるのに使う。 - 連番画像
画像ファイルをフレームごとに順番に読み込む。アニメーションテクスチャを作成可能。例:炎の連番画像を貼って燃焼アニメを再現。 - レンガテクスチャ
手続き型のレンガ模様を生成。色や隙間の幅、乱れ具合を調整できる。 - チェッカーテクスチャ
市松模様(白黒チェック)を生成。テスト用やシンプルな模様に便利。 - 環境テクスチャ
HDRIなどの360°環境画像を読み込み、ワールドシェーダーに適用する。実写ライティングや反射環境を再現可能。 - Gaborテクスチャ
ノイズの一種で、方向性を持つ模様を生成。フィルターや特殊効果に近い使い方。 - グラデーションテクスチャ
線形・放射・球形などのグラデーションを生成。ColorRampと組み合わせると便利。 - IESテクスチャ
照明器具メーカーが提供する IES配光データを読み込み、光の広がり方を再現。建築ビジュアライズで実用的。 - 画像テクスチャ
外部画像ファイル(PNG、JPG、EXRなど)を読み込み、UVマッピングで貼り付け。最もよく使うノード。 - マジックテクスチャ
サイケデリックな抽象模様を生成。正規用途は少ないが、実験的な表現や模様生成に使える。 - ノイズテクスチャ
標準的なノイズ模様を生成。RoughnessやBumpと組み合わせることで、自然素材の表現に欠かせない。 - 点密度
パーティクルやポイントクラウドの密度をボリューム化。煙や流体シミュレーションの可視化に使える。 - 大気テクスチャ
Blender標準の物理ベース空模様を生成。太陽の位置を設定してリアルな空ライティングを再現。 - ボロノイテクスチャ
細胞状・割れ目状の模様を生成。石材、肌、SF的パターンに使える万能ノード。 - 波テクスチャ
繰り返し波状のパターンを生成。縞模様、木目、水面模様などに利用可能。 - ホワイトノイズテクスチャ
入力座標を乱数に変換するシンプルなノイズ。各ポイントにランダム値を割り当てる用途で便利。
ベクトル
ベクトルノードは「位置・法線・方向」といった3D情報を変換・加工するためのノード群です。
テクスチャの伸びや歪み、バンプの強調、ディスプレイスメントによる変形などに不可欠。
- バンプ
白黒テクスチャを使って擬似的な凹凸(バンプマップ)を作成。法線情報に変換して、シェーダーの「Normal」に接続。 - ディスプレイスメント
入力テクスチャを元にメッシュを変形。マテリアル出力の「Displacement」に接続。 - マッピング
テクスチャ座標を移動・回転・拡大縮小。「テクスチャ座標」ノードと組み合わせて使う。 - ノーマル
法線ベクトルを調整するノード。法線を反転させたり、加工した結果を他のシェーダーに渡す。 - ノーマルマップ
外部で作ったノーマルマップ画像(青っぽいテクスチャ)を読み込み、法線情報に変換。プリンシプルBSDFなどの「Normal」に接続。 - ベクトルカーブ
入力ベクトルをカーブ操作で調整。RGBカーブのベクトル版。 - ベクトルディスプレイスメント
通常のディスプレイスメントは「高さ方向のみ」だが、これはXYZ方向に変形可能。 - ベクトル回転
入力ベクトルを任意の角度で回転。テクスチャの方向を制御する際に使用。 - ベクトル変換
座標系を変換する。例:ローカル座標 → ワールド座標、オブジェクト座標 → カメラ座標。
スクリプト
通常のノードと違い、外部で作成したスクリプトをマテリアル内で呼び出す特殊なノードです。
- スクリプト
OSL(Open Shading Language)のスクリプトを読み込んで利用するノード。Blenderの標準ノードでできない独自の処理やシェーダーを自作可能。Cyclesレンダー専用(Eeveeでは使えません)。
グループ
「グループ」カテゴリは、Blenderのノードネットワークを整理・再利用するための仕組みです。
複雑なノードをまとめて一つのノードのように扱えるので、効率化・整理・共有に役立ちます。
- 新規グループ
既存のノード群をひとまとめにした“箱”として扱う。自分専用のカスタムノードを作れる感覚。
レイアウト
マテリアルの見た目には直接影響せず、ノードの見やすさ・整理整頓のための補助的なノード群です
- フレーム
複数のノードを囲む枠を作る。フレームにラベルを付けておけば「ここは法線処理」「ここはベースカラー」などが一目で分かる。 - リルート
ノードの接続線を中継するだけのノード。線をきれいに整理して交差を減らせる。